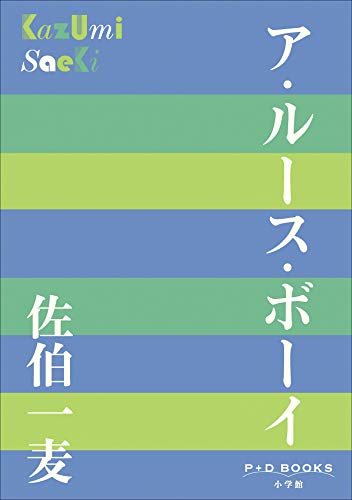あらためていうまでもない、ことのはずなのだ。
ぼくの最も嫌いなものは、善意と純情との二つにつきる。
考えてみると、およそ世の中に、善意の善人ほど始末に困るものはないのである。ぼく自身の記憶からいっても、ぼくは善意、純情の善人から、思わぬ迷惑をかけられた苦い経験は数限りなくあるが、聡明な悪人から苦杯を嘗めさせられた覚えは、かえってほとんどないからである。悪人というものは、ぼくにとっては案外始末のよい、付き合い易い人間なのだ。中野好夫「悪人礼賛」
中野好夫のことを否定するつもりはない、なんといっても中野好夫なのだ、というところがあり、そしてつぎに、このひとが書くから説得性を帯びる、というところがある、それが困りものだ。読んできて話すように話す勝手な人士というのが目立つから……。
その前置きを据えていって、今は、この時代性とはだいぶちがってきているのではなかったのだろうか。時代性、なのかねぇ……。とくに読書家に多いのだけれども、自分は自分をまちがっているとおもっている、だから賢いのだ、ということを中野好夫はここで言っているわけでは、けしてない。ここにあるのは開き直りの言葉ではなく、開き直りであったとしても開き直ったあとに本来、ぽつりとこぼされるべきであったひとつの訓話なのだ。もちろん、多くの人びとが、とくに作家達が、このように書いてきたわけであったが、それはめいめいの体験ののちに生まれたひとつびとつであったことを、私たち読み手は読みうしなってはならない。悪人こそが、善のいかさまを知る、不道徳こそが道徳の入り口なのであって、窃盗を指弾するのならば簡易だが、窃盗をした人間の窃盗の心地、後ろめたさ、罪悪感といったものは、だれよりもその当人が、窃盗者のひとりびとりが抱えるほかない宿業なのである。
その点で、西村賢太という私小説家は悪だと開き直ることを、おぼえてしまった人であった。自分は悪なのだから、なにをしてもいい、悪なのだから善意の人びとよりもさかしく生きているのだと、――それはたしかにそうだったであろうが、そこには反省が生まれない。佐伯一麦などを隣におくとわかるだろう。嫁さんのことを書いて、嫁にさんざ叱られ、ちがうんだこれは正しいんだ、いうなればそれが善なのだと説得を試みる、試みるということは悪を抱え込むということであり、悪と開き直ることによって投げ出してしまうこととは、大いに様相がことなるわけである。売女を買って知った売女の抱き心地を、どうどうと嫁さんにむけて投げ出してしまい、それをどうでい、と西村流に開き直るのよりも、小説のためなのだ、と説得をしてしまうことのほうが、美しい。美しいというよりも、じつは、したたかに、しかも屈託をふくんだ悪だったのではないか。